新約聖書のイエスはキリストとして描かれたイエスだが・・・
新約聖書はイエス・キリストについて述べているが、その言葉も行ないも、後の人の手によってキリストとして描かれたイエスである。イエス自身が書いたものではないし、イエスのそばにいた人がその場で記録したものでもない。
各文書の厳密な成立年は不明だが、どれも、イエスの没後、相当の年月が経過してから書かれている。著者も、パウロ書簡の一部を除き、よくわからない。
聖書は古代人が残した文書である。彼らは、我々とは違う古代の世界観の中に生きていた。聖書の著者たちと世界観を異にする我々は、もう、聖書の記述を文字通り信じることはできなくなっている。聖書の世界観は現代人の世界観とは相いれない。
「私たちは聖書を文字通り信じています」と言う人たちもいるが、そう言う人たちはかなり無理な解釈をしている。もし本当に文字通り信じることが可能なら、「文字通り信じる」人たちの見解はみなピタリと一致し、対立などないはずだ。だが、実際は、「文字通り信じています」と言う人たちが教派に分かれて対立し、同じ教派の中にさえ対立が見られることもある。
「どの教派でもいいのです」などと口では言いながら、違う教派で聞いた話をすると露骨に嫌な顔をする牧師や信者もいる。
真に文字通り信じるというのなら、書かれた当時の世界観に立つしかない。とは言っても、かなり多くの人々が聖書の執筆に加わっているから、執筆者たちのそれぞれの世界観も一致していない。聖書のある部分の著者の世界観に立てば、別の箇所の世界観との食い違いも起きる。
聖書の各部分がほぼ一致しているのは、この世界は、天界、地上、下界の三層からなっているという宇宙像である。どんどん空高く昇るなら、天界に行きつく。地面をどんどん掘っていけば、下界に行きつく。天界は神や天使たちの世界であり、下界は悪魔や悪霊たちの世界である。この地上が人間の住む世界であり、地上には天界の勢力も下界の勢力も出入りして、人間に影響を与えている、といったイメージである。
他にも、超自然的な奇跡や、種々の霊の存在も、聖書が書かれた当時の執筆者の世界観では当然の前提であった。
もし、我々が、聖書が執筆された時代の世界観を、当時の人たちと同じように信じるのなら、どうなるのだろう。
その場合、地球が丸いことや、宇宙には地球よりも大きな星があることや、ウイルスに感染して病気になること、その他の、近現代の科学が突き止めた種々の成果を否定的に考えないと一貫性がなくなる。
地球が丸いとは、聖書のどこにも書かれていない。星はいちじくのように落ちて来るというから、空の星はいちじくくらいの大きさだと考えるのが聖書的だ。ウイルスの話もまったく出てこないが、悪霊に憑かれた人、月に冒された人は出てくる。病気は、悪霊や月の作用によって起きると考えるのが聖書的だ、のようになる。
一方で聖書を文字通りに信じ、もう一方で科学の成果を信じようとするのは、都合の良い切り貼りのように思えてならなかった。
10代から20代初めの私は、イエスの教えに強く心をひかれながら、相容れないものを両方とも信じる信じ方が出来なかった。
私はどこまでも、一貫性・客観性を求めた。
最近、中村圭志著『信じない人のためのイエスと福音書ガイド』(みすず書房)という本を紹介していただいて、読んでいる。現在は版元品切れのようだが、古書で買った。著者は非クリスチャンだという。私は「信じない人」ではないけれど、この本はなかなか見事だと思いながら読んでいる。現代の聖書研究の成果を、素人にもわかりやすく書いている。まあ、私も素人だけれど。
おもしろくて、ついつい、夜遅くまで読んでしまう。
著者は非クリスチャンだから、信仰を前提にせずに、どこまでも客観的に書けるのだろう。
私も、聖書やキリスト教について何か言うときは、できるだけ客観的であろうと努めてはいる。各派のクリスチャンにも、非クリスチャンにも、伝わる言葉で語ろうと思っている。だが、私自身は、小学生のときに聖書に出会い、10代のときから「イエスの教えに従って生きていきたい」と思ってきた人間だ。そして、今もその思いから抜け出していない。だからつい「お祈りください」などと言ってしまうこともある。
私は、一貫性と客観性を大事にしたい。
そして、一貫性と客観性を大事にしながら、やはり、イエスの教えに従いたい。
そこに矛盾はないと思う。
参照「そんなイエスについていこうと思った」
http://yamazato.ic-blog.jp/home/2017/04/post-9c77.html
私は、農作業をしながら、ほとんど無意識に讃美歌を歌っているときがある。
(「讃美歌」338番)
主よ、おわりまで 仕えまつらん、
みそばはなれず おらせたまえ、
世のたたかいは はげしくとも、
御旗のもとに おらせたまえ。
うき世のさかえ 目をまどわし、
いざないのこえ 耳にみちて、
こころむるもの 内外にあり、
主よ、わが盾と ならせたまえ。
しずかにきよき みこえをもて
名利のあらし しずめたまえ、
こころにさわぐ 波はなぎて、
わが主のみむね さやに写さん。
主よ、今ここに ちかいを立て、
しもべとなりて つかえまつる。
世にあるかぎり このこころを
つねにかわらず もたせたまえ。
(「讃美歌21」57番)
ガリラヤの風かおる丘で
ひとびとに話された
恵みのみことばを、
わたしにも聞かせてください。
あらしの日波たける湖(うみ)で
弟子たちをさとされた
ちからのみことばを、
わたしにも聞かせてくだざい。
ゴルゴタの十字架の上で
つみびとを招かれた
すくいのみことばを、
わたしにも聞かせてください。
夕ぐれのエマオヘの道で
弟子たちに告げられた
いのちのみことばを、
わたしにも聞かせてください。
(伊藤一滴)
追記:「讃美歌21」57番の2番目の歌詞ですが、初期の版だと「弟子たちにさとされた」となってます。これは誤植です。正しくは「弟子たちをさとされた」です。
私が持っている誤植の版から引用していました。訂正します。
なお、カトリックの典礼聖歌にも同じ歌がありますが、そちらは正しく印刷してありました。
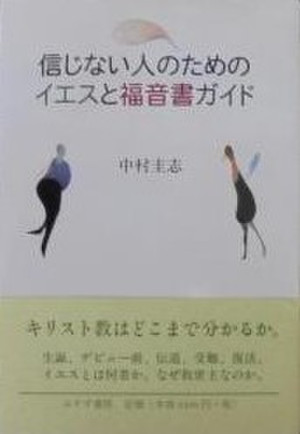
コメント