『「信仰」という名の虐待』再読
この夏、パスカル・ズィヴィー他『「信仰」という名の虐待』[いのちのことば社] をじっくり読み直してみました。
アマゾンのレビューにも書きましたが、もう少し詳しくここに書きます。
これは、福音派・聖霊派の教会のあり方に関わる問題です。
この本にそう書いてあるわけではありませんが、教会がカルト化して「信仰」という名の虐待が起きるのは、ほとんど、福音派・聖霊派の教会です。
プロテスタントの主流派(メインライン、つまりエキュメニズム派)やカトリック教会がカルト化したという話は聞いたことがありません。メインラインやカトリックの教会でも問題が起きることはありますが、どちらかと言えば、牧師や司祭の個人的な過ちであることが多いようです(個人的な過ちを許してしまう教会の体質を問題視する人もいるかもしれませんが)。
それに対し、一つの教会全体がカルト化してゆくのは、福音派・聖霊派の教会のあり方に関わる問題に思えます。
何度も言いますが、その団体が「正統」に分類されるのか「異端」に分類されるのかが問題なのではなく、カルトであることが問題なのです。カルト宗教は、その人自身とその人にかかわる人たちの人格や生活を踏みにじります。三位一体などの正統教義を認めるから正統派だ、正統派だから正しい、だから安心だ、みたいな、そんな話ではないのです。
それにしても、苦しみをかかえて「正統プロテスタントの教会」に助けを求めた人が、そこでますます傷を深くして、なんとか脱出しても、その後、後遺症に苦しむなんて…。ひどすぎるな、と思います。
もちろん福音派・聖霊派の牧師や信者の中に、穏健で善良で思慮深い方も多数おられます。私も、これまで、親切にしていただき、お世話になってきました。
福音派・聖霊派の信仰を否定する意図はまったくありません。
信仰の是非ではなく、なぜカルト化する教会があるのか、その要因だけを冷静に考えてみます。
カルト化の要因の一つとして考えられるのは、学問的な検討も含め「聖書批判を許さない体質」です。福音派・聖霊派の全員がそうだとは言いませんが、「聖書は絶対であり、信ずべきものであって、学問研究の対象ではない、批判など、とんでもない」という考えがあるのです。実は、聖書の記述にはいろいろと解釈の余地があるのですが、福音派・聖霊派の中には聖書批判を一切許さない人たちがおり、それが牧師批判を許さない体質になってしまうのではないでしょうか。聖書は絶対であり、聖書を解説する牧師の言葉も絶対で、批判してはならないものとなって、誰も牧師を止められず、教会が原理主義化し、カルト化していくように思えます。
リベラルなプロテスタント教会では、聖書を批判的に読むのも自由で、批判的な視点から書かれた注解書も多数出ています。最近は、カトリック教会も、現代的な聖書研究をふまえて語るようになってきました。たとえば、福音書の成立には伝承の過程があったこと、編集の過程があったことなど、カトリックでも常識レベルの話になってきました。
現代の聖書学をふまえ、批判的な目を持って聖書を読む人たちはカルト化しません。
もう一つの要因は、「福音派・聖霊派は総本部を持たない教会だから」です。連合組織はありますが、各教会を指導する本部ではありません。総本部がないというのは自由度が高いとも言えますが、それぞれの教会の牧師が勝手に聖書を解釈し、勝手にふるまうリスクも高い、とも言えます。小さな教派や単立教会では、さらにリスクが高まります。
総本部を持つカトリック教会や東方教会はカルトにはなりません。
(ものみの塔はアメリカに総本部を持っていますが、総本部自体がカルト的な主張をしているのでこれは別です。)
プロテスタント主流派も総本部を持たない諸教会ですが、どちらかと言えば知的で、学問的な水準の高い人が多く、知性、理性が重んじられています。19世紀の自由主義神学やその克服、弁証法神学(新正統主義)、様式史、非神話化、編集史、エキュメニズム、さらに宗教多元論の検討など、共通の、当然の前提になっています。
聖書に出てくる奇跡の話も、書いてあることを文字通り信じるというより、神話的な世界観の中で生きていた古代人の表現と考える人が多く、こうした知性・理性を重視する人たちはカルトになりません。
さらに、福音派・聖霊派と名乗る教会の中には「この世はサタンの支配下にある」と考えている人たちがいて、世の人(他教派も含めて)の指摘をサタンの声だと思ってしまうのです。小さく閉じた、彼らなりの「正しい信仰」の世界に、ますますこもってしまうようです。これはエホバの証人などのカルト信仰とよく似ています。福音派・聖霊派というより、自称「福音派」・自称「聖霊派」と言った方がいいのかもしれません。たとえ福音派の団体に加盟していたとしても、それは原理主義教会、あるいはカルト教会です。
聖書を読めば、矛盾するように思える箇所も多数あり、理屈のつけようで正反対の結論を導くこともできます。たとえば、戦争を否定するか肯定するか、奴隷制を否定するか肯定するか、死刑を否定するか肯定するか、女性の牧師を認めるか認めないか、同性愛者を拒絶するのか受け入れるのか…。もっともっとありますが、聖書を引用してまるで違う答えを出すことも可能なのです。
一牧師や、ある特定のグループだけの主張、聖書の言葉の一部のある種の解釈だけを絶対視しないようにしたいものです。
この『「信仰」という名の虐待』は、福音派の「クリスチャン新聞」に連載され、その後、いのちのことば社(福音派の出版社)から出されました。福音派による福音派内部の批判の書と言えます。勇気を持って、内部批判的な指摘をよくやってくれたと拍手を送りたい思いです。
原理主義の教会やカルト化した教会も、キリスト教と称し、プロテスタント教会と名乗り、多くの場合、福音派(または聖霊派)と称しているわけで、クリスチャン新聞や、新改訳聖書や、いのちのことば社の出版物などを買ってくれるお客さんでもあるのです。そういう一部のお客さんを正面から非難したわけで、喝采ものです。
ただし、福音派が出したものですから、私が上に書いたようなことには踏み込んでいません。そのあたりに、限界も感じます。
福音派の立場上やむを得ないのでしょうが、「教会がカルト化して「信仰」という名の虐待が起きるのは、ほとんど、福音派・聖霊派の教会です」と、はっきり書いてはいません。
(伊藤一滴)
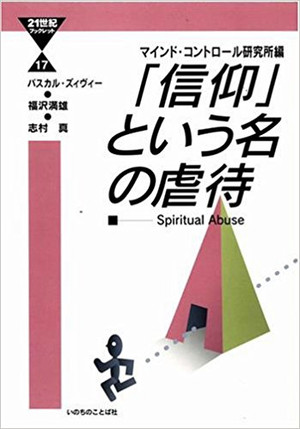
コメント