パッカー著『福音的キリスト教と聖書』を読む
J・I・パッカー(J.I.Packer)の『福音的キリスト教と聖書』(岡田稔訳 いのちのことば社)を読んでいる。これは実に興味深い本だ。なるほど、福音派の側からは、プロテスタントのリベラル(岡田の訳では自由主義、自由派)はこう見えるのかと、勉強になる。
原題は "Fundamentalism" and the word of God である。"Fundamentalism"と、引用符がついていて、そのまま題名を訳せば『「原理主義」と神の言葉』となる。もちろん、「根本主義」とも訳せるし、そのまま片仮名で「ファンダメンタリズム」としても、今は通じる。
でもなぜ、『「原理主義」と神の言葉』が日本では『福音的キリスト教と聖書』になってしまったのだろう。
聖書は神の言葉だと信じる人が、神の言葉=聖書、と言うのはわかる。
それなら、「原理主義」=福音的キリスト教、なのか。
福音的キリスト教と名乗る人たちの中には、原理主義者(ファンダメンタリスト)と言われても仕方のない人たちがいて、今も被害が続いている。福音派も注意を呼びかけているのに(例『「信仰」という名の虐待』)、いまだに、カルト思考の原理主義者らがあちこちにいて、ネット上でコメントしたり、キリスト教や聖書の入門のような形で盛んに発信したりしている。
パッカー自身は「自由主義の人たちから原理主義呼ばわりされている側」という意味で、引用符をつけて "Fundamentalism"としたのだろうけれど。
パッカーは、リベラルの側からのファンダメンタリズム批判は一貫していないと言うが、そりゃあそうだ。だって福音派自身、「福音派とは何か」の定義が一貫していない。だから見方によっては、極端な原理主義やカルトも含めて福音派となる。ペンテコステ派もカリスマ運動も福音派、セブンスデーアドベンチストも福音派、さらにエホバの証人だって広い意味では福音派、と見なすこともできる。それくらい、定義が一貫していない。
批判者の側の批判が一貫しないのは、むしろ当然だ。
(私自身は、福音派と原理主義を区別して考えているが。)
パッカーは、聖書の権威の論拠を聖書それ自体から引いてくる。これは、循環論法だ。かつて左翼学生が、マルクスの言葉を根拠にマルクスの正しさを論じたのと似ている。
また、パッカーが言うように聖書解釈の原理は聖書内にあって聖霊の働きで正しく解釈できると言うのなら、なぜ福音派同士で解釈が分かれて対立するのか、説明がつかなくなる。聖書が内包する矛盾の数々も説明がつかない。
聖書は伝承で補足されたり解説されたりする必要はないと言うが、一方で伝承を全否定もしない。そこにあいまいさもある。伝承に重きを置けばカトリック寄りになるだろうし、かと言って伝承を全否定すれば、カルヴァンが伝えたことも伝承、ウエストミンスター信仰告白も伝承、従来の聖書解釈も伝承と言われ、これらも否定すべき対象になりかねない。
まあ、1950年代に書かれた本を今の私が批判しても、後出しジャンケンになってしまうけれど。
聞いた話だが、岡田稔による日本語訳は、パッカーの原書(英語)から何箇所も削除された訳だという。原著は今でも買えるようだが、私は持っておらず、私自身は訳文と原著の比較検討をしていない。機会があれは、どこがどう削除されたのかを見てみたい。
でも、なぜ何箇所も削除したのだろう? 日本の福音派にとって都合の悪い箇所を削除したのだろうか?
削除は、日本の福音派団体の意向なのか、いのちのことば社の意向なのか、岡田が所属していた改革派(カルヴァン主義)教会の意向なのか、それとも岡田自身の判断なのか。
岡田は原著から何箇所も削除して訳したと、一言も言っていない。
削除版なら「パッカー原著、岡田稔編訳」とでも表紙に書くのが筋だろうに。
パッカーは、福音派の特に保守的な立場から、誠実に見解を述べたのだろう。私は、賛成はしなくとも著者の誠実さを感じる。だが、原著から何箇所も削除して訳しながら日本の読者に一言も言わない岡田稔の態度には、誠実さを感じない。
(伊藤一滴)
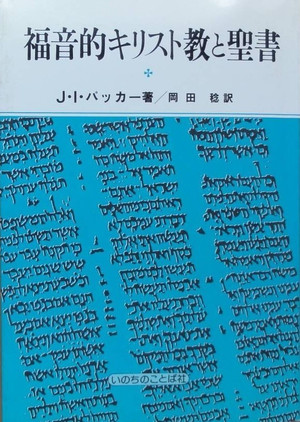
コメント